こんにちは。JICA海外協力隊を終え、海外大学院(ダブルディグリー・プログラム)に進学した、おぽきょです。
私の大学院生活は、フィリピンの「アテネオ・デ・マニラ大学」のオンライン授業から始まりました。
そして、結論から言うと、この3ヶ月は“地獄”でした。
「学問は一生終わらない会話なんだよ。」
教授のこの名言を胸に、私が「怒涛の3ヶ月」をどう乗り切り、何を得たのか。そして、その“地獄”を支えた**「3種の神器」**について、全公開します。
(※ちなみに、私が利用した日本財団の奨学金(APS)は残念ながら終了してしまいましたが、留学で得た学びは普遍的だと思うので、ここに記録します)
Contents
「オンラインなめてました」— The Beginning Is The Hardest
ウェビナーみたいに、先生の話を聞きながら課題をこなせば、なんとかなるだろう…。
正直、オンライン授業を軽視していました。
しかし、6月から始まった「英語強化クラス」と、7月から始まった「社会開発学」のクラスが重なり、私は“PC画面地獄”に叩き落されます。
腰が痛くても、目が乾いても、何時間も画面を見続け、毎晩23時に寝て、朝5時に起きる。一晩で論文(もちろん英語)を3本読み、翌日の授業で意見を言う。さらに、英語クラスの週2回のプレゼン準備と文献レビュー...。
「最初が一番しんどい」とは聞いていましたが、まさに始まった瞬間に正念場が来る、恐ろしい日々でした。
「正解はない」がルールの授業 — There Is No Right Or Wrong
そんな“地獄”の日々でも、授業そのものは、信じられないほど充実していました。
「社会開発学(Social Development)」というテーマは、人類学、社会学、経済学など、あらゆる視点を拾い上げた「ディスカッション」がメインでした。
そして、クラスの雰囲気が最高だったのです。
先生もクラスメイトも、驚くほど「異なる意見に寛容」でした。
「There is no right or wrong(正解も間違いもない)」
これが、全員の「暗黙の前提」でした。
たった一つの正解などない。100人いれば100通りの人生がある。全ての意見が、立派な「会話の素材」になる。
この温かい雰囲気のおかげで、引け目を感じるほど優秀な人々の中で、「JICA帰り」の私でも、自分の「現場経験」を元に、臆せず声を発することができました。
アテネオ大学のリアルな授業内容(社会開発学)
怒涛の3ヶ月で学んだのは、主に以下の3つの「モジュール」です。
① Key Concepts(開発の重要概念)
「開発」とは何かを、貧困、人権、ジェンダー、SDGsといった切り口で学びました。アジアの学者が書いた論文を多く読んだのが印象的です。
② Social Theory(社会理論)
個人的に、これが一番楽しかった授業です。
マルクス主義、新自由主義、マックス・ウェーバーなど、過去の学者の思想を元に「“開発”という概念が、どうやって確立されたか」を学びました。
③ Research Methods(調査方法論)
論文の「調査方法」のメソッドを学ぶ、レクチャー(講義)系の授業でした。(正直、これが一番難しかったです...)
【PR】“地獄の”オンライン授業を乗り切った「3種の神器」
この“地獄”の3ヶ月を、私がどうやって乗り切ったのか。
それは、この3つの「道具(神器)」のおかげです。これは、アテネオ大学を目指す人だけでなく、全てのオンライン学生・リモートワーカーに、心からお勧めしたい“投資”です。
神器1:iPad + Goodnotes(ペーパーレスの“最強脳みそ”)
オンライン授業の「課題図書」は、膨大な量の「PDF論文」です。
これをPC画面だけで読むのは、不可能でした。
私のワークフローはこうです。
- MACでオンライン授業を受けながら、教授のPPTをスクリーンショット。
- スクショがiPadに自動転送される。
- 「Goodnotes」アプリ(有料ですが、必須です)に、PDF論文と、PPTのスクショを読み込む。
- iPadとApple Pencilで、論文に直接「蛍光ペン」を引き、メモを「書き込む」。
紙を一切持ち歩く必要がなく 、全ての情報(論文、ノート)がiPad一つに集約される。この「ペーパーレス環境」がなければ、私は間違いなく“課題地獄”で溺れ死んでいました。
👇私の勉強を支えた「iPad」を見てみる
|
神器2:PCスタンド(肩こり・首痛との“決別”)
朝5時から夜23時まで、PC画面とにらめっこ 。当然、体はボロボロになります。
特に、MACの画面が低いと、姿勢が「猫背」になり、肩こりと首の痛みが悪化します。
「PCスタンド」を買い、目線をPC画面と“水平”にするだけで、肩こりは劇的に改善しました。これは「節約」してはいけない、「健康への投資」です。
神器3:FLSK(フラスク)水筒(“冷めない”白湯という“癒し”)
地獄のオンライン授業中、私の“心の拠り所”は、「いつまでも冷めない、温かい白湯」でした。
この「FLSK(フラスク)」という水筒は、保温力が驚異的で、朝入れた熱い白湯が、夜まで温かいままなのです。
部屋に篭りきりで、論文と格闘する合間に、この白湯を飲む「数秒」が、私のメンタルを何度も救ってくれました。
炭酸水が入れられる仕様になっており、保冷保温持続度は知っている限りこれが最強です。

ペルーへ旅行した際に無くしてしまい、代用の安い水筒を使っていましたがこれがないと不便で、帰国後にもう一度買い直し、今も愛用しています。そのくらいおすすめです!
👇私の“心の癒し”だった「FLSK水筒」を見てみる
|
まとめ:そして、コスタリカへ
このアテネオ大学での「地獄の(しかし、超・充実した)3ヶ月」でアカデミックな基礎体力と「3種の神器」を手に入れた後、私の舞台は「後半戦」のコスタリカ・国連平和大学(UPEACE)へと移ります。
コスタリカでの「ヤバい多様性」に揉まれた話は、また別の記事で。

コスタリカでは人も多様、自然も多様でたくさんの刺激を受けた
【次におすすめの記事】
この記事で「アテネオ大学」に興味を持ったあなたへ。
①【後半戦】この後に行った「国連平和大学」のリアルな授業内容
【実録】国連平和大学(UPEACE)の授業内容と“ヤバい”多様性
②【キャリアの全体像】私がJICA帰国後に「大学院」を選んだ“理由”
JICA海外協力隊「帰国後のキャリア」はどうなる?元隊員の私が選んだ「3つの道筋」と現実
③ 私が「大学院」を選んでも“お金の不安”がなかった理由
【全公開】手取り16.6万で資産1100万円。私の「全自動・資産形成術」
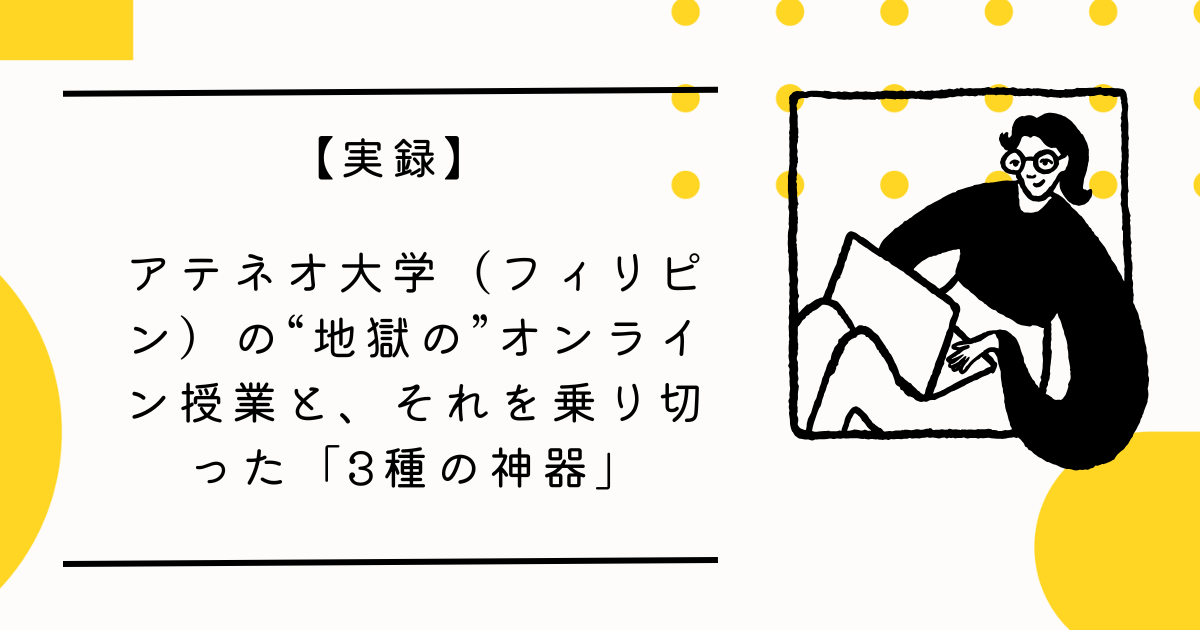
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dd2678a.8b58ef84.4dd2678b.5eecaf70/?me_id=1430870&item_id=10000583&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffs-mobile%2Fcabinet%2F11579609%2Fimgrc0103497614.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4dd26dd3.5c0c623b.4dd26dd4.e9638f9d/?me_id=1362821&item_id=10000004&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fimport-luxy%2Fcabinet%2F06814711%2Fimgrc0156931790.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
